きょうは67年目の「原爆の日」。
ヒロシマ・ナガサキの悲劇を描いた映画は多々ありますが、この作品も忘れがたいです。
以前、新聞『うずみ火』で掲載された拙稿をどうぞ。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
何と上品な女優さん……。
阪東妻三郎主演の『無法松の一生』(1943年)で、軍人の夫を亡くし、女手ひとつで男の子を育てる吉岡夫人に扮した園井恵子を、学生時代、銀幕で初めて眼にしたとき、正直、ぼくは胸の高まりを覚えた。
その彼女が映画公開の2年後、広島で被爆し、32歳の若さでこの世を去った。
『さくら隊散る』(88年)は、彼女が属していた戦時中の移動劇団、櫻隊の団員9人が原爆の犠牲になった事実を、再現ドラマと関係者の証言で構成したドキュメンタリー映画である。
監督・脚本は新藤兼人、ナレーターは妻の乙羽信子。
敗戦が濃厚になってきた44年末、大政翼賛会の肝いりで櫻隊が結成された。
演技派俳優の丸山定夫を隊長に、各地を訪問し、暗い戦時下、娯楽に飢えていた国民を楽しませた。
しかし団員のほとんどは戦前、社会主義的色彩の強い新劇の舞台を踏んでいたので、内心、屈辱感を覚えていた。
45年8月6日、広島に残っていた9人の団員が被爆した。
5人は即死、命からがら生き延びた4人の中に園井や丸山がいた。
彼らがいかにして死を迎えたか。
そのプロセスを、櫻隊結成のいきさつや当時のニュース映像を交え、この映画は淡々と伝えていく。
しかしモノクロの再現ドラマは形容しがたいほどに惨たらしい。
脱毛し、全身にバラ色発疹が生じ、やがてのた打ち回って悶絶死する。
園井恵子の最期……。
元タカラジェンヌとあって、宝塚歌劇団を象徴する『すみれの花咲くころ』の華やいだメロディーがかぶさる。
地獄絵のような映像とのギャップにぼくの心がかき乱され、涙がとめどもなくあふれ出た。
広島から東京へ逃げ延びてきた脇役俳優の仲みどりは、東大病院で死去した。
そして「原子爆弾傷」の第1号に認定された。
滝沢修、宇野重吉、小沢栄太郎、杉村春子、葦原邦子……。
生前に縁のあった俳優や関係者が、被爆死した4人についての思い出や無念さを赤裸々に吐露する。
そのひと言、ひと言がズシリと胸にのしかかる。
証言者の中で存命の人はもうほとんどいない。
演劇人の鎮魂歌――。
それは反戦の誓いでもある。

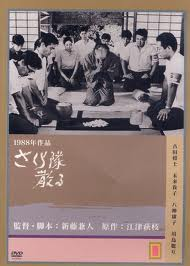
.bmp)
-縮小.jpg)
-300x225.jpg)
.jpg)

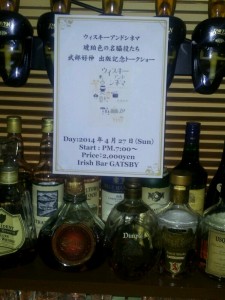


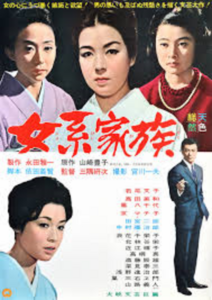


2009年に書いた拙文も転載しますねー(重複もありますがご容赦を)
ドキュメンタリーと再現ドラマを織り交ぜた作品。原作は1980年に江津萩枝が70歳で書いた『櫻隊全滅』(未来社)。
冒頭、東京・目黒の天恩山五百羅漢寺での法要から始まる。そこには「移動演劇さくら隊原爆殉難碑」がある。この作品では滝沢修や小沢栄太郎ら、「櫻隊」と縁のあった今は亡き名優たちが思い出を語る。
櫻隊は、1942年に誕生した苦楽座が前身で、45年に櫻隊と改名して移動劇団として活動を続けていた。丸山定夫を隊長とする11人のうち9人が広島にいた。
島木つや子、羽原京子、森下彰子、小宮喜代、笠絅子が即死、丸山定夫、高山象三、園井恵子、仲みどりが脱出するが、その4人も原爆症で間もなく相次いで死亡した。東大病院で死亡した仲みどりは「原子爆弾症第1号」として認定された。
この作品はもちろん原爆による人間的悲惨を描いたものだが、同時に戦時下の劇団がどのような管理下におかれていたかを伝える貴重な証言でもある。左翼的な劇団から出発した演劇人たちが、やがて大政翼賛的な時代に巻き込まれていく時代を今は亡き宇野重吉や殿山泰司、杉村春子、小沢栄太郎、滝沢修らが肉声で語っている。
突然リポーターとして登場する原作者江津萩枝さんも、2008年3月27日、97歳で大往生を遂げられた。
若くして志半ばで亡くなった俳優たちのことを語る人はもう殆どいなくなったという事実が、何とも切ないが、だからこそこの作品の持つ重みを再確認したい。時代が移り変わることによって逆に価値が生まれるドキュメンタリー作品だと思う。
名作・稲垣浩監督の『無法松の一生』(1943年)を観る度、私は未亡人を演じた園井恵子の最期を想起しないではいられない。