拾い物のアメリカ映画だった!!
こういう映画、理屈抜きに好きです。
大阪では、29日から梅田ブルク7で公開されます(R=15指定)。
ちょっと長いですが、本作についての拙稿をどうぞ。
時代背景がよくわかると思います。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
ノスタルジックな澱んだ映像の中に憂いが入り混じり、どこか危うさをかもし出す。
アメリカの禁酒法時代(1920~33年)を描いた映画には独特な空気が宿っている。
それは〈悪徳の匂い〉と呼べるかもしれない。
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(84年)、『アンタッチャブル』(87年)、『ミラーズ・クロッシング』(90年)、『ロード・トゥ・パーディション』(2002年)……、この時代のギャング映画はみなそうだ。
禁酒法は、酒を飲みたいという人間の根源的な欲望を道徳的・宗教的・経済的な理由で頭ごなしに抑え込んだとんでもない悪法だったとぼくは思っている。
文明のあるところ、かならず酒がある。
禁酒を強いるなんてことは土台無理な話。
当然、密造酒が造られ、酒の密輸が行われ、ヤミの酒場もできる。
そこには莫大な利権が絡み、無法者がわんさと出現した。
公開中の『華麗なるギャツビー』(2013年)もまさにその時代を活写していた。
主人公ギャツビーが主宰するセレブ階級のパーティーで出される酒の量はケタ外れだった。
また、『リバー・ランズ・スルー・イット』(92年)を観れば、どんな田舎町でももぐりの酒場があったことがわかる。
禁酒法時代のアメリカ国民のアルコール消費量は、それ以前よりもはるかに上回っていたそうだ。
さて、『欲望のバージニア』。
本作は禁酒法解禁の2年前(1931年)、密造酒を製造・販売する3兄弟の物語である。
舞台は中東部バージニア州のフランクリン郡。
映画の中で説明されていたように当時、この辺りは密造業者(スマグラー)のたまり場で、「世界の密造酒の首都」という異名をとっていたという。
フランクリン郡のある村では住民100人中、なんと99人が密造と関わっていたといわれている。
現在、バージニア州では公認のウイスキー蒸留所は1か所だけだが、依然として密造酒がいたる所で造られているらしい。
ぼくはウイスキーをはじめ洋酒の文化にいたく興味をもっている。
しかも魅惑的な禁酒法時代の物語とあって、この設定だけで本作に魅せられた。
内容も思いのほか濃厚だった。
この映画は拾い物だとつくづく実感した次第。
前置きが長くなった。
本題に入ろう。
「絶対に死なない」
どんなことがあろうとも、自分たちは不死身であると自負するポンデュラント3兄弟の生き方を描く。
飼っている子ブタを殺す冒頭シーンから、3人3様、個性的なキャラクターを浮かび上がらせる。
長男ハワード(ジェイソン・クラーク)はいたって寡黙で、酒ばかりあおっているが、ひとたびキレると、猛烈な暴力をふるう、ちょっと恐ろしい男だ。
猛獣と表現してもいい。
次男のフォレスト(トム・ハーディ)は冷静沈着に物事を見据える眼力をもっており、ある意味、3兄弟のリーダー格である。
長男に劣らず、凄まじい腕力の持ち主で、ブラスナックル(金属製のメリケンサック)をはめて容赦なく相手を打ちのめす。
彼ら2人に比べ、三男のジャック(シャイア・ラブーフ)は見るからに優男で、非力さが際立つ。
しかし要領がよく、抜け目がない。
裏でこそこそ暗躍する野心家タイプだ。
自分の存在感を示そうと躍起になるところが可愛いらしいが、悲しい哉、思慮に欠け、常にトラブルの元凶になる。
この男の行動が物語の伏線になっている。
彼らが造っているのが「ムーンシャイン(Moonshine)」とか「バスタブ・ジン(Bathtub gin)」とか、そんな風に言われる粗悪な酒だ。
「ムーンシャイン」というのは夜半、山間部において月夜の下で、「バスタブ・ジン」は風呂桶の中に蒸留器入れて、それぞれ造っていたからそう名づけられた。
アメリカでは密造酒の代名詞になっている。
原料はコーン(トウモロコシ)、カブ、カボチャ、樹皮など。
それらを簡単な蒸留器を使ってきつい蒸留酒にする。
アルコール度数は優に60度を超える。熟成していないので、見た目は透明。
要は焼酎やウォッカと同じだ。
ただし、風味はひどかったに違いない。
「上物のコーン・ウイスキーだ」というセリフがあったが、今のバーボン・ウイスキーとは似て非なるものである。
ジャックの親友で発明家のクリケット(デイン・デハーン)が作った大型蒸留器には目を見張った。
山間の小屋に3基の蒸留器がズラリと並ぶさまは、まるで正規の蒸留所のようだった。
あんな密造所が実際にあったのか、非常に気になる。
当時、酒を造れば、間違いなく売れる。
それゆえポンデュラント3兄弟は無法なスマグラーとして、またヤミ酒場の経営者として生計を立てている。
「バージニアの中でもとびきり美味い酒」とPRし、密造仲間から一目置かれているが、それでも実入りが少ないのか、暮らし向きはいたって貧相である。
彼らはいわゆるプア・ホワイト(貧しい白人)だ。
禁酒法時代の最中、1927年に大恐慌に見舞われる。
その時代の前半は『華麗なるギャツビー』に象徴される狂騒の時代、後半は本作で描かれるような不況の時代。
空気がまったく異なる。
しかも都会と田舎。
両者を比較すると、格差がよくわかる。
密造酒の運搬に車が使われるが、地方の泥臭い雰囲気からして、何だか西部劇のようなたたずまいがする。
そうなんだ、禁酒法時代のアウトロー映画は、20世紀の西部劇!
だからゾクゾクしてしまうのかもしれない。
それが本作のベーシックなトーンになっている。
兄弟の住居兼酒場が素晴らしい。
ガソリンスタンドを買い取ったらしく、使い尽くされた給油機が建物の前にポツンと屹立している。
埃っぽいテラスはいかにも西部劇に登場しそうな感じ。
酒場の中のやたら広いフロア、簡素なテーブルとイスもしっくり合っている。
汗と血と男の匂い。
それらが木目に染み込んでいる、そんな味わいだ。
シカゴから赴任してきた捜査当局の特別補佐官レイクス(ガイ・ピアース)が高級車に乗って、3兄弟の前に姿を見せた瞬間、ドラマがにわかに転がり出す。
その場面が実に強烈だった。
公然と高額の賄賂を要求するのだ。
お金をくれたら、密造を黙認する。
権力者を揶揄し、悪人のごとく描写するのはこの手の映画の常套手段だが、ここではそれをとことん強調する。
三つぞろえのスーツを着こなし、首元には蝶ネクタイ。
そして両手にはめられた革の手袋。
頭の真ん中でべったり分けたテカテカの黒髪をいつも気にしている。
このキザっぽいスタイルをレイクスは最後まで崩さない。
超ナルシストで、喋り方と仕草がどうにも嫌味ったらしく、陰湿さを滲み出している。
ひと言で言えば、トカゲのような男だ。
応対に出たフォレストが賄賂の要求をすげなく断るや、レイクスに怒りの炎が燃え盛る。
その時の表情の変化が見ものだ。
こういう人間はひと一倍プライドが高い。
バージニアの住民を人間と思っていないだけに、なおさら自尊心を傷つけられ、ムキになる。
そして徐々に残虐性をむき出しにしていく。
そこに執念深さが加わるのだからやっかいだ。
ポンデュラント3兄弟VSレイクス。
権力に抗う無法者。
この構図が非常にわかりやすい。
兄弟に理解を示しながらも、立場上、レイクスに協力せざるを得ない人のいい保安官が両者のあいだで翻弄される。
その様が実におかしい。
この対立関係だけでも十分、見ごたえがあるのに、さらに魅惑的な人物を3人添える。
そのキャスティングにうならされる。
ひとり目が流れ者の女マギー(ジェシカ・チャスティン)。
街で踊り子をしていたが、ワケありで兄弟の店に来て、雇ってほしいと懇願する。
儚げでハスっぱ、どこか翳りのあるところが妙に艶っぽい。
ビンラディン殺害を描いた実録物『ゼロ・ダーク・サーティ』(2012年)で、彼女が演じたCIAの敏腕アナリストとは対照的な役どころだ。
フォレストに惹かれ、強引に迫っていくところは鳥肌が立った。
ふたり目が牧師の娘バーサ(ミア・ワシコウスカ)。
見るからに無垢な生娘丸出しで、ジャックとのプラトニックな関係が何とも初々しく、一種の清涼剤のような役割を果たす。
父娘が信仰しているのが18世紀初め、ドイツで生まれたダンカー派というキリスト教(プロテスタント)の一派。
酒に関しては比較的寛大だが、道徳的な戒律が厳しく、当然、無法者との恋沙汰はご法度。
彼女の父親にとっても、ジャックの兄たちにとっても、2人の恋愛はよく思われていない。
そこが程よい味付けになっていた。
そして3人目がギャングの大物フロイド・バナー(ゲイリー・オールドマン)だ。
白昼、車で町に乗り込むや、いきなりトミーガンをぶっ放し、敵対するギャングを射殺する。
何と鮮烈なシーン!
平然と町を去っていくとき、ニヤリと笑みを浮かべる不敵な面構えに惚れ惚れする。
オールドマンならではの存在感だ。
超大物のこの男が陰でポンデュラント兄弟をサポートする辺りがニクイ。
レイクスがジャックを虫ケラ同然、徹底的に痛めつけ、さらにフォレストとマギーにも手を下したことから双方の激突が時間の問題となる。
首をかき切られ、なおも生き抜いたフォレストの生命力は凄いとしか言えないが、同時に笑ってしまった。
そんなことあり得ないと。
でもええんや。
彼らは不死身なんやから!
やがて兄弟にとって家族同然のクリケットがレイクスに殺されたことで壮絶な復讐劇が始まる。
レイクスの弱者に対する非情な態度がドラマを沸点へと導く。
クライマックスへのお膳立ては申し分ない。
この展開もひと昔前の西部劇らしい。
巧い!
ジョン・ヒルコート監督は、文明が崩壊した近未来の世界を放浪する父子を描いた『ロード』(2009年)と同様、ここでも有無を言わせず極限状態にもっていく。
『マジソン郡の橋』(1995年)で日本でも知られるようになった古風な屋根付き橋が戦いの場となる。
木々の緑の中、こげ茶色の橋が格好のランドマークとして浮き上がる。
古色蒼然と言おうか、少しくすんだシックな色調の映像が時代を感じさせる。
3兄弟の性格は異なれど、絆は鋼鉄のようにめっぽう強い。
そこに加勢が入り、まさにアウトローと警察権力の全面戦争といった様相だ。
しかしスタイリッシュなアクション映画とは対極の非常に泥臭い銃撃戦が展開される。
あっ気なく弾丸に当たり、あっ気なく倒れる。
スローモーションで撮れば、もっと迫力が出るはずなのに、変に誇張しない。
あくまでも生身の人間のぶつかり合いを見据える。
これは忘れ得ぬ名場面になった。
この映画は実話だ。
ジャックの孫が執筆した小説を映画化したもので、ポンデュラント兄弟は今でも「バージニアの伝説」になっているという。
歪んだ権力に対し、どこまでも不撓不屈の精神で立ち向かう。
それを痛快さではなく、骨太さで描き切った娯楽作である。
観終わったあと、男っぽい粗野な香りで胸が満たされた。
あゝ、まるで密造酒のように……。
(大阪映画サークル 第1272号 2013年6月15日)









-576x1024.jpg)
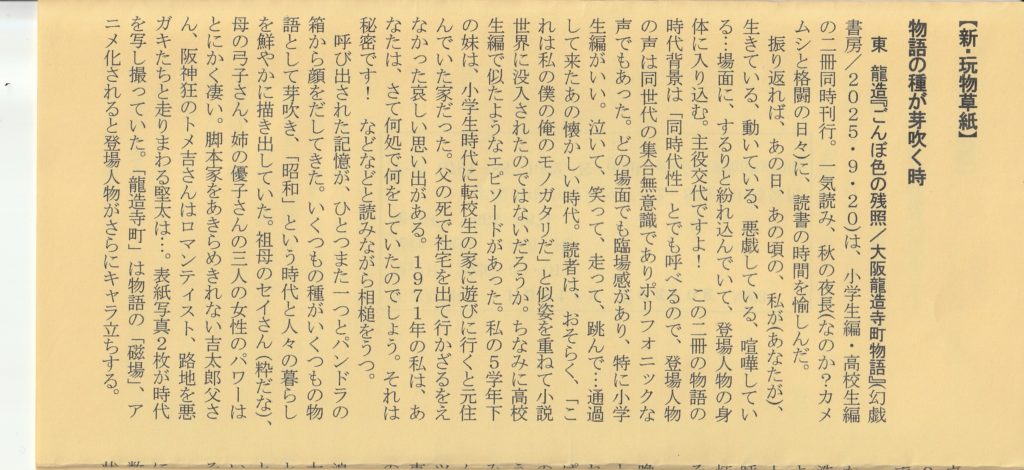


ウイスキー&シネマ-1024x784.jpg)