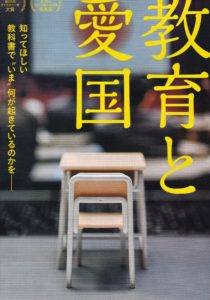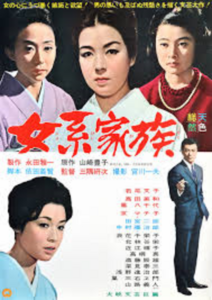大阪ストーリー(10)実は……、身近な上方伝統芸能(2019年9月)
☆道頓堀ミュージアム並木座
インバウンド(外国人観光客)で賑わう道頓堀。世界各国の言葉が飛び交い、「大阪もえらい変わりようや」と思いながら、3月末に開館した「道頓堀ミュージアム並木座」に入りました。
その瞬間、400年前にタイムスリップ!
そこには江戸時代の芝居小屋の空気が充満していました。
道頓堀といえば、かつては歌舞伎と文楽の劇場が軒を連ねる芝居の町。
とりわけ浪花座(竹本座)、中座、角座、朝日座、弁天座の「道頓堀(浪花)五座」が有名でした。
近年、寄席・新喜劇の常設館や映画館に様変わりし、今では松竹座しか残っていないのが寂しくてたまりません。
その道頓堀で、世界に先駆けて廻り舞台やせりを考案した江戸中期の歌舞伎狂言戯作者、並木正三(しょうざ)を顕彰するため、街づくり事業を展開している山根秀宣さんがこの博物館を建造されました。
展示を見入っていると、「日本のブロードウェイ」だった遺産を風化させてはならじという山根さんの気概が感じられ、いつの日か道頓堀に劇場文化を復活させてほしいと願わずにはいられませんでした。
廻り舞台で石川五右衛門に変身し、日本語に堪能なネパール人のガイド、パサン・ラマさんの説明を受けているうち、最近、上方伝統芸能にあまり接していないことに気づきました。
いや、これまで歌舞伎、文楽、能、狂言、落語は折に触れて鑑賞してきたけれど、浪曲、上方講談、上方舞はというと、正直、遠い世界でした。
よっしゃ、この機会にどっぷりハマったろ~!
☆浪曲~一心寺門前浪曲寄席
そう思って、まずは一心寺南会所(天王寺区逢坂)に足を向けました。
そこで月に一度、「一心寺門前浪曲寄席」が開かれているのです。
若さみなぎる京山幸乃(ゆきの)さんが三味線の音色に合わせて声を張り上げる。
演目は相撲取りの物語『雷電と八角』。
歌っているような語り(啖呵)のあとにメロディーに乗って大熱唱(節)。
感極まると、「イョーッ!」と客席から声が飛び交い、拍手が巻き起こる。
すべて575のリズムで、とても聴きやすい。
どことなく演歌に似ており、心がくすぐられます。
声色、顔の表情、仕草を観ているだけでも面白い。
まさにワンマン歌謡ショーですね(笑)。
演じ終えた幸乃さんが楽屋に下がると、先輩格の春野恵子さんが「あの場面では顔をあまり動かさない方がいいよ」とアドバイス。
それに対し、「はい、はい」とうなずく幸乃さんは埼玉県人。
この寄席で2代目京山幸枝若(こうしわか)さんの浪曲に魅せられ、1年前に弟子入りしたばかりの新人さんです。
「覚えるだけでもしんどいです。声の出し方もまだまだ。カラオケルームにこもって日々、練習」
十分、声に張りがあると思うのですが……。
プロの道は厳しいですね。
現在、大阪に約30人の浪曲師がおり、そのうち女性が13人。
「私の歌芸を聴いて幸せな気分になってもらえる、そんな浪曲師になりたいです」
大きな目がさらに見開いた。ぼくは心の中で彼女の背中をグッと押しました!
☆上方講談~此花千鳥亭
次に訪れたのが今年1月3日にオープンした此花千鳥亭(此花区梅香)。
大阪で80年ぶりに復活した講談の専門劇場、しかも全国初とあって、ひじょうに気になっていました。
『講談ひるず』と題する昼席で、旭堂南龍さんが伝説的な彫刻師と絵師の話『甚五郎と探幽』、この定席建設に奔走した女性講談師の5代目旭堂小南陵さんが妖狐(ようこ)の化身を題材にした『玉藻前発端(たまものまえほったん)』を読み、満席の観客を沸かせてくれました。
張り扇(おうぎ)を釈台にたたきながら、響くように読んでいく「修羅場読み」はやはり講談の醍醐味ですね。
迫力満点で、気圧(けお)されました!
笑いを提供する落語とは異なる一人話芸。
共に八尾出身のご両人に一番大切な点はなにかと訊くと――。
南龍さんは「間です。空間の、そして自分の間。気ともいえますね」
小南陵さんは「間とよく似ていますが、私は役割りと呼んでいます。それにリズム感」
ふーん、そうなんや。
それではズバリ、講談とは?
「笑いがないのに、こんだけ聞かせる。これぞ究極の伝承芸です」と南龍さんが言えば、小南陵さんも「自分の身一つで、いろんな空間を創り出せる。やはり究極の芸能ですね」
なるほど!
一時は大阪で講談師が1人だけになったときがありましたが、今は90人ほどいるそうです。
お2人から熱い〈オーラ〉が感じられ、すごくうれしくなりました。
蛇足ですが、張り扇は東京では和紙、こちらは牛革か合成皮革を使っていることを教えてもらい、なんだか得した気分に……。
☆上方舞~お稽古場
締めは上方舞。これまで数えるほどしか接点のなかった世界です。
大阪で創流された山村流の山村若静紀さんのお稽古場(西区九条南)を興味津々、見学させてもらいました。
上方(京都と大坂)で生まれた上方舞は能にゆかりがあり、お座敷芸として発展しました。
それに対し、「踊り」は歌舞伎から派生し、江戸で人気を博した舞台芸です。
「舞」と「踊り」。
2つを合わせて日本舞踊。
そのことを知ったとき目から鱗が落ちました。
「お顔は正面ですよ」
「扇、真っすぐに」
「細(こま)こうに、細こうにやりましょ」
めでたいときに披露する『高砂』の舞いを学ぶお弟子さんに対面指導する若静紀さんのはんなりとした声が稽古場に飛び交っていました。
上方舞は心情を表現する身体芸といわれています。
「型と振りは表裏一体。まずは型をしっかり覚えることが肝要です。自分が楽しんだらダメ。抑制の芸能なんです」
わっ、そうなんや!
皆さん、立ち居振る舞いがほんにお美しい。
お弟子さんたちの上方舞に対する感想は――。
「伝統芸能と関われたのがうれしい」
「クラシックの洋舞を指導していますが、いろんな共通点を見出すのが楽しいです」……。
さらにこんな含蓄のあるコメントも。
「物事を考え、実際に行動する際の一つの指針なのかもしれません」
深いです。
舞いを観ているうちに、ぼくの心が知らず知らずのうちに和らいできました。
不思議な作用があるんですね。
「上方舞はわかりやすいです。だからもっと間口を広げていきたいですね」
こう願う若静紀さんの表情がじつにすがすがしかった。
これらの伝統芸能を生み、育んできた大阪は紛れもなく成熟した街です。
しかも身近に触れることができるのですから、極めて文化的な街ともいえます。
若い人たちがしっかり芸を受け継いでおり、少なからず若い観客も楽しく受け止めていたのがとてもうれしく思いましたが、国や行政、その他諸々のサポートがなければ、健全に芽吹いていきません。
文化は「都市の顔」。
そのことを痛感しました。
並木座-576x1024.jpg)
並木座-1024x576.jpg)
並木座-1024x576.jpg)
並木座-1024x576.jpg)
浪曲一心寺-1024x576.jpg)
浪曲京山幸乃-1024x907.jpg)
講談千鳥亭-1024x576.jpg)
講談ご両人-1024x576.jpg)
上方舞稽古-1024x576.jpg)
上方舞山村若静紀-1024x576.jpg)